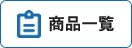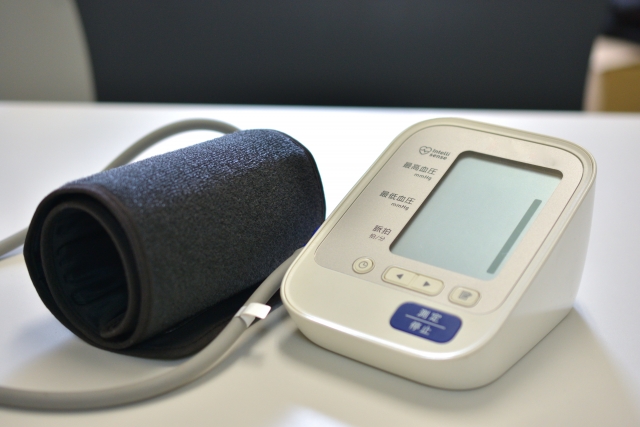機能性表示食品を総まとめ!トクホとの違いや表示に記載ある内容は?

トクホの製品はコンビニやドラッグストアなどで見かけることも多く、耳なじみがあると感じる人も多いでしょう。
しかし、実際に機能性表示食品がどのような製品なのか詳細を把握できていますか?
この記事では、機能性表示食品とトクホとの違いや内容などを紹介します。
機能性表示食品とは
機能性表示食品の制度が施行されたのが2015年4月1日です。それまでは、特定保健用食品(トクホ)と、国の規格基準に適合した栄養機能食品のみは食品の機能性について表示が認められていました。
機能性表示食品は事前に届け出するよう定められており、食品の安全性や機能性など条件を満たすことで表示が可能になります。
消費者庁による審査や許可などを必要としないため、特定保健用食品よりも届け出が簡単になったことが特徴です。
機能性表示食品の表示に書かれている内容
この段落では、機能性表示食品の表示に書かれている内容について詳しく説明します。
パッケージ表
パッケージの表には機能性表示食品と表示され、届け出番号や科学的根拠を基にした機能性について消費者庁長官に届け出た内容について表示されています。
また、「脂肪の吸収を穏やかにします」という内容や「「おなかの調子を整えます」といった摂摂したうえで期待できる内容についてもわかりやすく記載されています。
パッケージ裏
パッケージの裏には、1日あたりの摂取目安量・製品が医薬品ではない旨・事業所の電話番号などが記載されています。
疾病がある人や妊産婦に向けて開発された商品ではないことが注意事項として明らかにされています。1日あたりの摂取目安量を摂取した場合、どれくらいの機能性関与成分が摂取できるのかが記載されているため、使用する際の目安になるでしょう。
機能性の表示ができる食品
この段落では、機能性の表示ができる食品の種類について紹介します。
機能性表示食品
機能性表示食品は、加工食品やサプリメントの他にも魚や果物などの生鮮食品も含まれています。お茶やパン類に表示されるものもあり、日ごろの食生活から取り入れやすい食品に多い傾向があります。
ドレッシングにも表示されているものがあるため、サラダなどに取り入れることで野菜を美味しく摂取しやすくなるでしょう。脂肪や糖分の吸収を抑える食品もあるため、疾病による体調管理を必要としている人にとって利用しやすい食品だといえます。
特定保健用食品
特定保健用食品は、疾病の治療や予防を目的としたものではないことが特徴です。ヨーグルトや豆腐などの発酵食品、緑茶や青汁などの飲料も特定保健用食品はあります。腸内環境を整え、健康の維持・増進に働きかける機能がある食品が多い傾向です。
消費者庁による審査や許可などを経ているため、食品としての信頼感があり摂取しやすいといえます。
栄養機能食品
栄養機能食品とは、ビタミンなどの栄養成分の摂取を補うために利用する食品のことを指します。サプリメントや栄養ドリンク、乳酸菌飲料などに表示されることがあります。シリアルバーなども販売されているため、気軽に軽食やおやつとして摂取することもできます。
カロリーゼロのゼリーなども販売されており、体重制限がある人などは日々の食事に取り入れやすいことが特徴です。便秘になりやすい女性や高齢者は、ビタミンB12や食物繊維が多く含まれている栄養機能食品を選ぶようにしましょう。
まとめ
高血圧をはじめとする生活習慣病を予防するためには、日々の食生活や運動などの生活習慣を見直す必要があります。しかし、1日に必要な栄養素を食品から摂取することは難しいケースも多いですよね。
食事だけで補えない栄養素などについては、機能性表示食品などを上手に活用するようにしましょう。機能性表示食品のサプリメントを使用することで1日に必要な栄養素を補い、身体のなかから健やかな状態へと導きやすくなります。