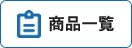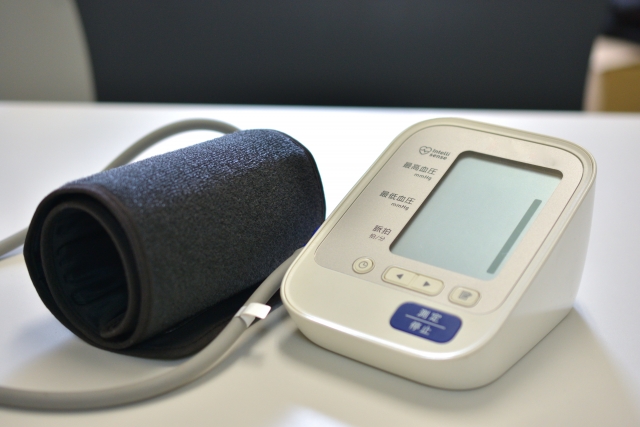高血圧は診断基準でチェック!診察室血圧ごとのリスク層別化に見る高血圧

「血圧」とは血液が血管を押す力のことで「高血圧」とはその力が一定の基準より強いことを言います。高血圧はさまざまな病気につながることが多いため、早いうちから対策をしたいものです。
しかし、対策をするにしても、その基準とは一体どれくらいのものなのでしょうか?今回は、高血圧の診断基準やリスクに関して解説しましょう。
高血圧の診断基準
血圧は常に変化するものです。起床時、日中、睡眠時、と身体活動や精神活動の変化に応じて刻々と変化しています。血圧は季節によっても変わることがあるので、一度高い数字が出たからといってすぐさま高血圧と診断されるわけではありません。
病院で測ったり家で測ったり、繰り返し検査していく中で診断されます。その診断基準は、日本高血圧学会が発表している「高血圧治療ガイドライン」で細かく定められています。まず大まかに分けて「診察室血圧」と「家庭内血圧」の2つがあります。前者は病院などで測る血圧、後者は家で測る血圧です。環境の変化によって血圧は変化するのでこのように分けています。
ここでは診察室血圧について解説していきます。
診察室血圧によるリスク層別化
血圧は数値で分けられるだけでなく、既往症など血圧以外のリスク要因に応じて第一層~第三層に分けられます。血圧が正常値であっても、第三層に区分されるなどリスクが高い場合には高血圧と診断されることもあります。第一層であればリスク要因がないとされるので、判断材料となるのは血圧の数値のみです。
http://www.osaka-ganjun.jp/health/cvd/hypertension.html
第一層Ⅰ型
最高血圧が140~159 mmHg、最低が90~99 mmHgの人はⅠ型に分類されます。高血圧と診断される人の中では軽度ですが、だからといって油断はできません。血圧が上140 mmHg下90 mmHgを超えると途端に心臓や血管の病気になる人が増えるからです。Ⅰ型であれば、生活習慣の改善をしっかり行うことが大切でしょう。
https://www.healthcare.omron.co.jp/resource/guide/hightbp/02.html
■出典:日本高血圧学会
https://www.jpnsh.jp/data/jsh2014/jsh2014_gen.pdf
第二層Ⅱ型
Ⅱ型の基準は最高血圧が160~179 mmHg、最低が100~109 mmHgです。この数値になると、第一層であっても脳心血管病(心筋梗塞や脳卒中といった、心臓、脳の血管にまつわる病気の総称)のリスクは中程度まで高まります。医師の指示に従い、日々の生活の見直しをするなど、適切な対策をしていきましょう。
https://www.healthcare.omron.co.jp/resource/guide/hightbp/02.html
■出典:公益財団法人 大阪がん循環器病予防センター
http://www.osaka-ganjun.jp/health/cvd/hypertension.html
第三層Ⅲ型
Ⅲ型は最も危険な区分で、最高血圧が180 mmHg以上、最低血圧が110 mmHg以上の人を指します。第Ⅲ型になると、第一~三層のどの層にいる人であっても脳心血管病は「高リスク」とされます。そのまま放っておけば、ある日突然、くも膜下出血や心筋梗塞などで倒れてもおかしくはないのです。高血圧は「サイレントキラー」といわれることもある病気で、自覚症状がないまま第Ⅲ型まで進行してしまうこともあります。診断を受けたら速やかに治療を開始しましょう。
高血圧の基準の推移について
日本高血圧学会は高血圧治療ガイドラインを5年ごとに改定しています。2019年の改定版では高血圧の診断基準は2014年に発表されたものと変わっておらず、最高血圧140 mmHg以上、最低血圧90 mmHg以上がその基準です。
一方、合併症がない75歳未満の降圧目標については引き下げられ、上が130 mmHg、下が80 mmHgとなりました。これは日本における基準ですが、世界保健機関(WHO)の発表している数値も同じです。
一方、国によって独自の基準を設けているところもあります。例えばアメリカの場合、2017年に米国心臓病学会/米国心臓協会が発表したガイドラインによれば高血圧と診断されるのは最高血圧130 mmHg以上、最低血圧80 mmHg以上とされています。人種による違いがあったり、その国独自の生活習慣があったり、さまざまな背景から独自の診断基準を設けている場合があるのです。
https://www.dietitian.or.jp/trends/2019/86.html
まとめ
高血圧は気付かないうちに症状が進むことがある恐ろしい病気。健康診断などでの数値を気にするだけでなく、機会があれば積極的に測ることが望ましいでしょう。上記で挙げた基準を参考に、もし気になる数値が出たときにはすぐに医師に相談してくださいね。