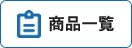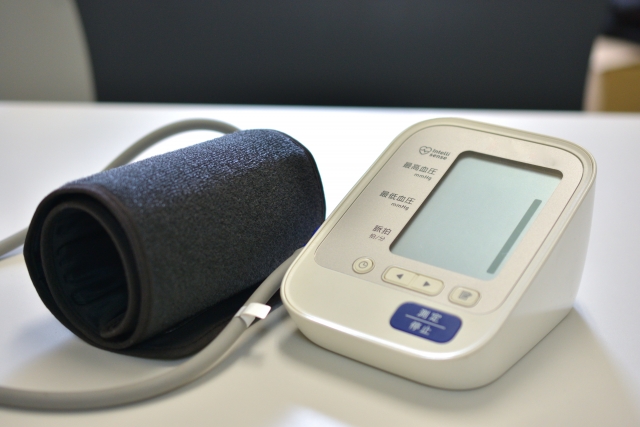季節の変わり目やお風呂場に潜む「ヒートショック」のデメリット

季節の変わり目や冬場などは、ヒートショックを起こしやすい環境が多く、注意する必要があるといわれています。
そもそもヒートショックとは具体的にどのような症状なのか、そして、どのような対策が考えられるのかを詳しく説明していきます。
ヒートショックとは
ヒートショックとは、周囲の温度が大きく変化した際に体が受けるダメージのことをいいます。高齢者や体の弱い人はヒートショックを起こしやすく、重大な疾病を引き起こす原因にもなるため注意が必要です。ここでは、ヒートショックの症状や起こりやすい環境について説明します。
ヒートショックの症状
ヒートショックが起きると、失神などの症状のほか、不整脈や心筋梗塞、脳梗塞などを引き起こすケースもあります。失神の場合であってもそれが入浴中であれば湯船で溺れる他、脱衣所の場合などでは転倒し怪我をするなどの恐れがあるでしょう。
ヒートショックが起こりやすい環境
ヒートショックは温度変化の大きい環境でよく発生する傾向にあります。日々変化する気候に体が対応しきれない季節の変わり目なども気をつけましょう。
特に、必要な時間以外に使用しないトイレや浴室などは、ヒートショックが起こりやすい場所として知られているのです。冬は体を温めようと熱めのお湯に浸かる人も多く、その分ヒートショックが起きる危険性も高まるようです。それに冬場は、暖房の効いた部屋から効いていない場所に移動する際など、温度差によってヒートショックが起こりやすくなるといわれています。
また入浴の際には、寒い脱衣所で服を脱いだときに血圧が上がり、湯船に浸かって体を温めたときには血圧が下がり、浴室から寒い脱衣所に出たときに再び血圧が上がってしまうというように血圧の変化が大きく、ヒートショックが起こりやすいので注意が必要です。
http://www.kagoshima.med.or.jp/people/topic/2010/308.htm
■出典:独立行政法人 労働者健康安全機構
https://ehimes.johas.go.jp/wp/topics/4418/
ヒートショックのメカニズム
気温の高い場所から気温の低い場所に行くと、血管が縮むことによって血圧が上昇がみられるでしょう。また、気温の低い場所から気温の高い場所に行った場合には、血管が広がることによって今度は血圧が低下する傾向に。
このような気温の高い場所や低い場所への出入りによって血管が収縮を繰り返し、血圧の変動が続いた場合に、ヒートショックが起こりやすいと考えられています。
また、普段から血圧の高い人の場合、血圧値が正常の人よりも血圧変動が大きくなる懸念があるのです。
http://www.hcc.keio.ac.jp/ja/health/2009/12/20091201.html
■出典:独立行政法人 労働者健康安全機構
https://ehimes.johas.go.jp/wp/topics/4418/
ヒートショックの対策
ヒートショックは、重大な疾病を引き起こす原因にもつながる恐れのある症状です。しかし、対策をたてることでヒートショックを起こすリスクを減らせるでしょう。
それではヒートショックの対策について見ていきます。
ヒートショック・プロテイン
ヒートショックプロテインとは、熱の刺激によって作られるたんぱく質で、損傷した細胞をケアする働きを持ったものです。ヒートショックプロテインは、入浴やサウナなどによって作り出され、免疫力を高めることができることから、ヒートショック対策にも役立つといわれています。
入浴の場合、約40~42度のお湯に20分程かけてゆっくりと浸かるとヒートショックプロテインが作られる傾向にあるでしょう。しかしこの際に、熱いお湯に浸かると血圧が上がってヒートショックを起こしてしまう恐れがあるので、湯温を上げないよう気をつけなければいけません。
暖房器具の活用
ヒートショックの原因として挙げられる、大きな温度差ができる環境を作らないためには、暖房器具の活用が大切。脱衣所やトイレなど、使用する際以外には入らない場所なども暖房器具を設置しておけば、部屋を移動したときの温度差を少なくできます。
https://www.otsuka.co.jp/suimin/hsp70.html
■出典:東洋経済オンライン
https://toyokeizai.net/articles/-/147324
■出典:ココカラファイン
https://www.cocokarafine.co.jp/f/dsf_howto201506009905
まとめ
ヒートショックは、暖房の活用やヒートショックプロテインの力などの対策で、起きるリスクを低く抑えられると考えられています。冬場や季節の変わり目は特に注意して、自身や家族の身を守るようにしましょう。